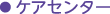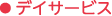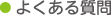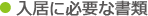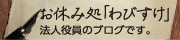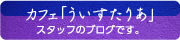今はもう秋 誰もいない海♪♪♪ トワ・エ・モアの唄う名曲は、中年以上の高齢者にとっては深い哀愁を掻き立てられる歌であろう。あの暑かった夏が終わり、凌ぎ易い季節がやってきた。秋は実りの秋、食欲の秋、読書の秋でもある。食べ物が美味しく、「天高く馬肥ゆる秋」でもあり、「人も肥ゆる秋」でもある。旬の美味しい物を食べると健康になるという意味から「柿が赤らむと医者が青くなる」「サンマが出るとあんまが引っ込む」とも言われている。
「秋茄子は嫁に食わすな」「秋サバは嫁に食わすな」と言った諺もあり、美味しい茄子や旬のサバを嫁に賞味させるのはもったいないと言った嫁いびり説や茄子は体を冷やすから、またサバは食あたりしやすいので大事な嫁の食膳に出さないようにと言った嫁擁護説が言い伝えられている。
読書の秋にちなんで古書を紐解いてみると、山夕(さんせき、下の句が「秋の夕暮れ」で終わる有名な三つの句のこと)という文字が目に入ったので紹介させていただく。
寂しさは その色としもなかりけり 槙立つ山の 秋の夕暮 (寂蓮法師)
見渡せば 花も紅葉もなかりけり 浦の苫屋の秋の夕暮 (藤原定家)
心なき 身にもあわれは知られけり 鴫立つ沢の 秋の夕暮 (西行法師) (大磯町にある鴫立庵が、西行法師が吟遊中にこの句を歌った場所である、ここで売られている西行饅頭は得意な格好をしており、一度食してみる価値がある)
また、秋には「秋の七草」なるものがある。「春の七草」は「七草粥」にして食べるなど“食”を楽しむものであるが、「秋の七草」は花を“見る”ことを楽しむものとされている。この「秋の七草」は山上憶良が万葉集の歌で選定し、今に至っている。
秋の野に 咲きたる花を 指折り(およびおり) かき数ふれば 七種(ななくさ)の花 萩の花 尾花 葛花 撫子の花 女郎花 また藤袴 朝貌(あさがお)の花 (朝貌は朝顔ではなく「桔梗」であるとの説が定説)
「秋」をひとつ紐解くだけで、歴史をたどり、古きを尋ねる旅に出ることができるのである。これが現代になると、「一日千秋」「物言えば唇寒し秋の風」「女心と秋の空」「秋の夜と男の心は七度変わる」等々変わってくるものである。しかし、そうは言っても「和」をもってホスピタリティーを実践する介護の世界には、「秋風が吹く」と言った諺は近寄ってもらいたくないものである。
そして、秋といえば日本の大衆魚「秋刀魚」が真っ先に頭をよぎる。 落語に出てくる「目黒の秋刀魚」のように、炭火で焼かれた「尾頭付き」の秋刀魚は、血行を良くし、脳梗塞や心筋梗塞を予防し、悪玉コレステロールを減らす効果のある成分を多く含む。秋刀魚の頭と尾を切り落とし、フライパンの大きさに合わせて焼かれた現代風の秋刀魚は、お江戸の殿様でなくとも敬遠したいものである。
落語に出てくる「目黒の秋刀魚」のように、炭火で焼かれた「尾頭付き」の秋刀魚は、血行を良くし、脳梗塞や心筋梗塞を予防し、悪玉コレステロールを減らす効果のある成分を多く含む。秋刀魚の頭と尾を切り落とし、フライパンの大きさに合わせて焼かれた現代風の秋刀魚は、お江戸の殿様でなくとも敬遠したいものである。
伊藤 克之









![yjimage[6]](https://dooshare.xbiz.jp/wp-content/uploads/2014/08/yjimage6.jpg)
![yjimage[1]](https://dooshare.xbiz.jp/wp-content/uploads/2014/08/yjimage1.jpg)

![img51[1]](https://dooshare.xbiz.jp/wp-content/uploads/2014/07/img511.gif)
![roujin_syokuji[1]](https://dooshare.xbiz.jp/wp-content/uploads/2014/07/roujin_syokuji1-460x350.png)